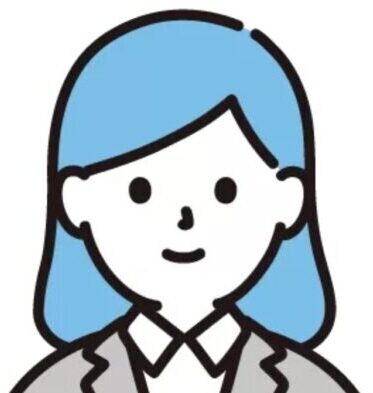ほぼ毎日何らかの映画を観ている司法書士です。先日ケーブルテレビをつけたら映画『ぼくの美しい人だから|White Palace』が流れていました。昔、小説も読みました。この地味で哀愁漂う恋愛映画を知っている人は少ないでしょう。邦題が秀逸です。
あらすじと基本情報
妻を事故で失った27歳のエリート広告マンのマックスと43歳のハンバーガー店員のノーラ。年齢も育ちも全く違う二人が、偶然の出会いから一夜の関係を経て、次第に純粋な愛を育んでいく大人のラブストーリー。どこを取っても不釣り合いなはずだった二人のリアルな恋愛模様を繊細に描く。
| 原題 | White Palace |
| 公開年 | 1990 |
| ジャンル | ロマンス |
| 監督 | ルイス・マンドーキ |
| キャスト | ジェームズ・スペイダー、スーザン・サランドン |
| Amazon Prime Video | 配信 | 〇 |
| U-NEXT | 配信 | × |
| YouTube | 配信 | 〇 |
| TSUTAYA DISCAS | 宅配DVDレンタル | ○ |
ラブストーリーと絡めた脱出劇
“ラブストーリーと絡めた脱出劇”ーこれが本作の真骨頂ではなかろうか。最初からネタバレしてしまうが、ラストはきっちりハッピーエンドを迎える。
ラストシーン、それまで色々あって離れ離れになった二人だが、マックスがノーラが新しく働くカフェを突き止め、勤務中の彼女に愛を告げる。ここだけ取り出せば『プリティ・ウーマン』(1990)と激似の王道パターンに思えるが、この映画の肝は表面的なラブストーリーを超えている点にある。マックスはかつて属したユダヤ社会、エリート広告会社、そして裕福な暮らしという「絵に描いたような安定」から思い切って決別したのである。
それは、まるで長年、心の中で重くのしかかっていた「憑き物」が呪縛から解き放たれたような解放劇。いわば制服を脱ぎ捨て、縛られた良識という鎖を断ち切った瞬間なのである。お気楽シンデレラ映画『プリティ・ウーマン』とは、この点でまったく違う。『プリティ・ウーマン』も、「男は運命の女と出会うことによって開眼する」という似たようなプロットではあるものの、リチャード・ギア演じる「男」は最終的にちょっとした価値観の広がりがあっただけで、あくまでも恋愛中心の物語で人の心の問題には深入りしない。
これまで多くのカネと成功を手に入れながらも、逆にその重責とストレスに押しつぶされ、心の満足を得られなかったマックス。彼が生きていたのは「見せかけだけの安定生活」、実は冷たく閉ざされた心の牢獄である。この牢獄からの脱出宣言が、ノーラという別階層・別価値観の女性を選ぶことで示される。
まさに冒険の始まりであり、これまでの自分をそっくり捨て去る意思表示だ。これは単純な年の差恋愛の枠を軽々と超えた、人生の「大革命」である。ここで思い出したいのはフランス映画『汚れた血』(1986)のアレックスが運命の女アンナに放った名セリフ、「今君とすれ違ったら、世界とすれ違う」。マックスとノーラの関係もまた、重層的な社会的・感情的溝を超える「運命的出会い」を象徴している。
ゆえに、マックスがノーラを迎えに行く場面は、彼の「社会的檻」からの完全な脱出かつ「新しい自分」への飛翔を意味し、単なるハッピーエンドとは一味違う深みを持つ。ジェームズ・スペイダーの繊細な演技により、人生の苦悩と決断、再生のストーリーが雄弁に語られている。
総じて『ぼくの美しい人だから|White Palace』は、表面的な恋愛を越えて、階層・価値観の壁を乗り越えた「真の愛と自己発見」の普遍的なドラマであり、心に響く「脱出劇」なのである。
ジェームズ・スペイダーという変態紳士の進化史
ジェームズ・スペイダーほど、「狂気と上品さ」を同じトレイにのせられる俳優はそういない。彼のキャリアを振り返ると、整髪料できっちり撫でつけられた青年が、気づけば禁断の地下室へと自ら降りていく――そんな奇妙な進化の物語が見えてくる。
彼の初期は、とにかく「金持ち学校の嫌なやつ」だった。80年代青春映画の代表作『プリティ・イン・ピンク』(1986)や『レス・ザン・ゼロ』(1987)では、サングラスにジャケット、マティーニを飲みながら、「君たち庶民とは違うんだよ」と言ってのけるタイプ。だが、そこに漂う冷淡さは、ただの金持ちではなく、何か哲学的な変態性を孕んでいた。観客は彼を嫌うふりをしながら、なぜか気になってしまう。
デビュー作は1981年の『エンドレス・ラブ』。ここでは、ブルック・シールズの兄役で、彼のキャリアでは珍しく「至ってまともな役」。しかし、この作品はクセもの中のクセもの。世間的には何となく「ブルック・シールズ美少女黄金期のロマンチック青春映画」とされているが、実際の中身はもはやラブストーリーを装ったサイコドラマ。恋を親に反対された彼氏が、思い詰めた末に恋人の家に放火して全焼させるという、倫理も理性も炎上の展開である。
「家を燃やすほど好きだなんて」と聞くと、いかにも甘いメロドラマの台詞に思えるが、本作では文字通り火をつける。恋愛の比喩が文字通りの犯罪になる時点で、すでに物語は破綻している。出演者の誰一人としてまともな決断をしない中、スペイダー演じる「恋人の兄」だけが唯一理性的で、観客の最後のよりどころになる。つまり、彼の俳優人生を知るにつれ、『エンドレス・ラブ』において彼が唯一「まともな人」というのは、スペイダーの俳優史を考えると信じがたいほど貴重な立ち位置である。
さらに拍車をかけるのが、あの有名な主題歌。ライオネル・リッチー&ダイアナ・ロスによる史上最強(そして最甘)デュエット「Endless Love」。二人の声が絡み合い、永遠の愛をこれでもかと熱唱するさまは、もはや酸欠レベル。恋を燃やすどころか、命の危険があるほど燃え上がってしまう若者たちの姿と重なって、現代の観客からするともはや笑うしかない。 ライオネル・リッチーが目を閉じて陶酔し、厚い唇を震わせながら拳を握るたびに、「いや、全然そんな映画じゃない」と内心総ツッコミ。これほど劇中と主題歌の整合性が取れていない映画も珍しい。甘美なラブソングが、悲劇的狂気を包み込むという、ある意味では奇跡的な組み合わせだった。こんな超甘ラブソングを聴かされた後は、Queenを聴くかゆらゆら帝国を聴くか、はたまた「ミナミの帝王」を観るかして甘くなった脳内と現実とのバランスを取り戻すことが必要。
ともあれ、この“恋の放火事件”映画で唯一まともだったスペイダーは、後に安全圏をあっさり捨てる。主にアンドリュー・マッカーシーをイジメるインテリいじめっ子として80年代アメリカ青春映画を駆け抜ける。
1989年、『セックスと嘘とビデオテープ』で次のステージへ進化。同作でカンヌ映画祭主演男優賞を受賞。他人の性体験を記録するという倒錯的な行為を、品よく、知的に、そして奇妙に哀しく演じてみせた。覗き魔のようでいて、どこか聖職者めいた寡黙さがある。彼が口を開くたび、観客は「禁欲と欲望」という矛盾の渦に引きずり込まれていく。どの物語の役もそうかもしれないが、この役が成立するにはあくまでも「二枚目であること」が必須。
こうしてスペイダーは、「正統派二枚目」の道から完全に逸れ、「変態紳士」としての確固たる地位を築いていく。『ぼくの美しい人だから|White Palace』のマックスはまさにその進化の途中段階。まだ社会的にはまともで、心の翳りも人間的な範囲に留まっている。だが、すでに理性と感情の境界線がほころび始め、「壊れかけて社会の隅に行こうとする」男を丁寧に体現した。ノーラとの出会いは、冷たく閉ざされたマックスの精神を一度壊し、再構築するための火の粉のような存在だった。
そして、彼はこのまま変態路線まっしぐらかと思いきや、1994年のSF大作『スターゲイト』に出演。いい意味で予想を裏切ってくれる。そもそもそれまで大作娯楽作品とは無縁だった。トム・クルーズ的な俳優ではない。興行的には中ヒットくらいではなかったか。この作品に出演したこと自体、彼の俳優人生の中でも意外な一幕であると言えよう。さらに、考古学者(博士)というロジカルな職の人を演じることも珍しかった。博士は、古代エジプトの神秘的な謎を解き明かし、「スターゲイト」と呼ばれる宇宙への扉を発見する。この作品では体育会系のカート・ラッセル演じる大佐との対比が極めて鮮やかで、博士は『セックスと嘘とビデオテープ』での青年役の延長線上にあるとも言えなくもない。彼の役は繊細で内向的な知性派キャラクターであり、あの作品で見せた「陽」の部分が進化した姿である。静かな鋭さと知的好奇心に満ちた彼の演技は、『スターゲイト』というSF大作の華やかな冒険譚の中でも確かな存在感を放っている。
その後、彼は、『クラッシュ』(1996)でディープな倒錯ワールドへ大ジャンプ。自動車事故が性的倒錯とくっついてしまうという、まさにクローネンバーグ監督の“マニアック趣味”が炸裂した世界の体現者となった。事故とエクスタシーの融合という摩訶不思議な話を、彼は静かにそして真剣に演じた。私には『クラッシュ』の映画としての良さは全く理解できなかったが、この作品の倒錯男のキャラクターも『セックスと嘘とビデオテープ』での青年役の延長線上にあるとも言えなくもない。つまり、『スターゲイト』が彼の「陽」の進化形ならば、『クラッシュ』は「陰」の深化形という構図で捉えることができるかもしれない。なお、この「車と性的倒錯」という設定、最近どこかで聞いた事ある・・・と思ったら、『TITANE/チタン』(2021)。頭にチタンを埋め込まれた女性が車と性行為をして妊娠するという更に奇天烈な作品。車に性的魅力を感じる監督は他にもいるのですね。
『セクレタリー』(2002)では、支配と服従の果てにある“美学”まで咲かせる上司役に進化。ここまで来ると、もう“変態の様式美”が完成したと言わざるをえません。何を演じても清廉で知的、しかし心の奥底はいつだっておそろしく壊れている。そう、ジェームズ・スペイダーとは「理性の仮面をかぶった危険物」。
彼の演じる役柄にはいつも「エレガントな狂気」という香りが漂い、それを嗅ぎつけたファンはみんな虜に。映画の中で不思議と「お行儀よく壊れている」彼の存在感は、まるでオーケストラのなかの斬新なソロパートのように光り輝いている。
『ぼくの美しい人だから|White Palace』のマックスは、ジェームズ・スペイダーが変態的なキャラクターへ寄って行く過程において、まだ「(変態へ)振り切れていないが片鱗が見えてくる」稀有な存在。愛によって痛みを知り、激情を通して理性を取り戻す。その過程で見せる笑みは美しく、同時に哀しい。スペイダーほど“人間の弱点をエレガントに演じる男”は他にいない。そして、そんな彼の出発点に『エンドレス・ラブ』という放火ラブストーリーがあると思うと、人の道のりというのは実に面白いものである。