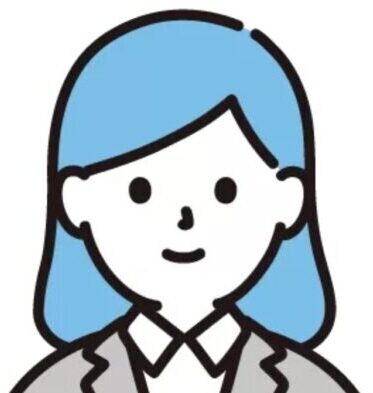ほぼ毎日何らかの映画を観ている司法書士です。ケーブルテレビで『ロード・オブ・ザ・リング』シリーズエクステンデッド・エディションが放映されいて、1作品が公開版よりもさらに長い4時間程ありました。連続で全3作観賞すると一日仕事になります。
あらすじと基本情報
ホビットの青年フロド・バギンズが、伯父ビルボから受け継いだ「指輪」を巡って仲間たちと共に冒険に出る。それは、邪悪な冥王サウロンの復活を阻止するため、「指輪」を滅びの山で破壊する旅だった。「指輪」の魔力は強大で、仲間たちの間に亀裂を生じさせる中、エルフ、ドワーフ、人間ら多彩な仲間と共に幾多の危機を乗り越える様を描く。壮大なファンタジーアクション巨編3部作。
| 原題 | The Lord of the Rings |
| 公開年 | 2001-2003 |
| ジャンル | ファンタジーアクション |
| 監督 | ピーター・ジャクソン |
| キャスト | イライジャ・ウッド、ショーン・アスティン イアン・マッケラン、ヴィゴ・モーテンセン |
| Amazon Prime Video | 配信 | 〇 |
| U-NEXT | 配信 | 〇 |
| YouTube | 配信 | 〇 |
| TSUTAYA DISCAS | 宅配DVDレンタル | ○ |
ファンタジー映画の集大成
1980年代半ば、私は小学校3年生だった。当時スピルバーグは最初の全盛期を迎えていた。最初のスピルバーグの記憶は86年公開の『グーニーズ』である。偶然にも、『ロード・オブ・ザ・リング』の忠実で賢い従者サムを演じるショーン・アスティン主演の大ヒット冒険映画である。
『グーニーズ』は少年たちの物語である。遊園地のような映画で、『スタンド・バイ・ミー』のような感傷的な部分はほとんどない。あくまでもエンターテイメントに徹した子供向け娯楽作品。カラっとした楽しさで満ちていた。その時、スピルバーグは絶好調で、既に『未知との遭遇』『E.T.』『インディ・ジョーンズ』で、冒険・SF・ヒューマン・ファンタジーを融合させて一大ムーブメントを巻き起こしていた。彼の作品は「ありえないもの(UFO・恐竜)」を現実に感じさせ、童心と冒険心を刺激し、映画館を「魔法の体験空間」に変えた。子どもも大人も等しく夢中になる普遍的エンタメ要素を映画作品に盛り込んで革命をもたらした。
ファンタジー映画の発展には、スピルバーグと双璧をなすジョージ・ルーカスの功績も大きい。80年『スター・ウォーズ』でSFとファンタジーを融合し、家族・運命・善悪・伝説的な騎士道…という普遍テーマを銀河スケールで描いた。(と言っても、私は未だに『スター・ウォーズ』をまともに通しで鑑賞したことがない。積極的に観なくてもそのうち機会があるでしょう。)
ファンタジー映画の流れは、1970~80年代スピルバーグによる娯楽の革新期と、ルーカスによるSF全開世界観の創造を経て、2000年代『ロード・オブ・ザ・リング』で集大成の頂点を迎えたと言っていいかもしれない。中間を相当飛ばしているけれども。
この先人たちの“現実を超えた冒険・神話・人間ドラマの融合”は、CGやVFX技術をふんだんに駆使することによって、ピーター・ジャクソンによる『ロード・オブ・ザ・リング』三部作で一気に結晶する。精緻な世界観と壮大なビジュアル、日常の小さな者が世界の運命を動かすという逆説、そして「欲望との闘い」という根源的テーマ──スピルバーグやルーカスのファンタジー遺伝子を全方位に受け継ぎ、多層的な感動を生み出した。
『ロード・オブ・ザ・リング』三部作は、「ただのファンタジー映画」なんて言葉では到底片づけられない超大作である。そもそもスタート地点は、ホビットという背丈ちっちゃめ、平和大好き、胃袋に定評あり、という何とも人間味あふれる(人間じゃないけど)存在たち。彼らの村の牧歌的日常から物語は始まるわけだが、この点が実に絶妙だ。最初ののんびりムードがあるからこそ、あとのモブ(群衆)シーン連続のド派手な戦いとの落差が効いて、観客は「のんびりお茶してたホビットたちがここまでの旅に!?」と驚かされる。
この構成は、まさに古典的な冒険譚の出発点。子どもが観てもワクワクするし、大人が観れば「平和の日常のありがたさ」が胸にしみる。ここから怒涛の冒険が展開するわけだが、作品全体を包み込むのは「ファンタジー」という殻をかぶった“リアルな人生模様”。剣と魔法が飛び交っていても、観客が見つめるのは極めて人間的な感情のぶつかり合いなのである。
因みに、『グーニーズ』の俳優陣には沢山の子役・若手俳優が出演していたが、その後俳優として大成したのは、主人公の兄役のジョッシュ・ブローリンでしょう。コーエン兄弟の『ノーカントリー』で「おかっぱ頭の殺し屋」ハビエル・バルデムに執拗に追われる元溶接工の役どころが特に良かった。主人公の仲間の少年役キー・ホイ・クアンも何十年ぶりかに復活して2022年『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』でアカデミー助演男優賞を受賞。
ゴールは「指輪を捨てる」こと
『ロード・オブ・ザ・リング』の核にあるのは、ひと言で言えば「欲望にどう向き合うか」というテーマ。作中で「指輪」は究極の権力を授ける代物だが、同時にそれを持つ者を必ず堕落させていく呪いの象徴でもある。権力欲、名誉欲、物欲、承認欲求…現代を生きる私たちも日々大なり小なり手にしている「指輪」をどう扱うかに苦しむのだ。
フロドの旅とは、すなわち「欲望という荷物を担ぎ、それを棄てるための旅」である。だが、フロド自身も最後の最後には指輪の魔力に屈してしまう。そこに描かれるのは、人間が完全に欲望を制御することの難しさだ。
この寓話性は、単なるファンタジーの枠を大きく超えている。『ハリー・ポッター』が「勇気と友情」で困難に立ち向かう青春物語であるのに対して、『ロード・オブ・ザ・リング』はさらに根源的で難解なテーマ――「人間の欲望と破滅、そこから逃れる可能性とは何か」――に挑んでいる。より深淵でシリアス。それゆえ、この物語を最後まで観たあとに我々に残るのは「冒険の余韻」と同時に「人生の問い」なのである。
「指輪=依存症」
前項は「指輪物語」についての一般的な解釈である。この物語を発展的かつ今日的な問題から解釈してみよう。
指輪とは人に宿る欲望、特に支配欲を象徴しているものだが、もう少し身近な視点で考えると「指輪=依存症」と置き換えて見る事ができるのではないか。すると、実はとてもブラックユーモアに富んだ依存症克服物語に見えてくる。旅の大義名分は「世界を救う」だけれども、当人たちの実態は「悪魔的魅力を放つ麻薬じみた指輪とどう距離を取るか」という、自己破産待ったなしの依存症患者の奮闘劇と捉えることもできるだろう。
まず指輪。これが完全に「キマる危険ドラッグ」や「ギャンブル」そのもの。ちょっと触れただけで瞳孔は開くし、人間関係は破綻し、持ち主は「俺だけはやめられる」と豪語しながら深みに沈む。フロドが「重くてつらい」と呻くのは、実際には禁断症状。しかも指輪は本人だけでなく、周囲の人間にも「一口いいだろ?」と誘惑してくるので、まるでカジノで友達を巻き込むギャンブラー。恐ろしいのは「持っているだけで気分が良くなる気がする」という点で、依存症者が財布を握りしめながらパチンコ屋に入っていく時の恍惚感そのもの。
そんな指輪に憑かれたフロドは中つ国版依存症患者。指輪という名の“合法危険ドラッグ”――または“誰も勝たないギャンブル台”にハマった青年の苦闘は、依存症患者の日常ドキュメントそのもの。フロドの一挙手一投足は、依存症患者の行動をデフォルメした上質なブラックコメディ。「あと一回だけ…」と言いながら足音を忍ばせて指輪に近づく様は、パチンコ屋の開店ダッシュに匹敵。そして「これを持っていれば大丈夫」と持ち歩き出すフロド。ギャンブル依存の「少しの小遣いがあればパチ屋直行」と同じロジックを見ているよう。
一方、サムは「支援者」であり共依存の家族。フロドが汗にまみれて「もう無理だ……」と弱音を吐くたびに、「フロドさま!あなたはできます!」と必死に励ます。まるでパチプロにハマった息子を叱咤しつつ食費を差し出すお母さんのよう。本人以上に真剣だ。物語後半でサムがほぼ「指輪を持たせてください、私が代わりに我慢します」と言い出すのは、まさに家族も一緒に依存症を抱え込む「共依存」そのもの。そして、サム自身も実は依存症の渦に巻き込まれていく。
さらにゴラム(スメアゴル)。彼は完全に「依存症の成れの果て」を戯画化した存在だ。禁断症状で二重人格になり、かつてホビットだった自分(健康だった頃)と現在の妖怪と化した自分を一人で演じ続ける姿は、まるで自助グループの体験談をそのまま映像化したよう。普通なら悲惨でしかないのに、やけにコミカルに描かれていて、人間の滑稽さを浮かび上がらせる。
また、依存症からの回復に必須とされる「仲間」や「環境からの隔離」も映画の重要テーマ。フロドが一人で頑張ろうとすると、即アウト。ところがサムをはじめ支援者と一緒なら、何とか踏みとどまれる。アルコール依存症で「飲み友達」から距離を置く必要があるように、彼らもモルドールに入ってからは「誘惑の街」そのものの黒門を避け、遠回りしてリハビリ施設みたいな険しい山道を選択する。これが依存症克服の鉄則「環境を変える」にそのまま重なっているのは興味深いところだ。
最も皮肉なのが結末。数々の苦難を乗り越えて滅びの山の火口にやっとたどり着いたフロド。しかし、フロドはついに「指輪を捨てる」ことができない。つまり最後の最後で誘惑に負けてしまう。にもかかわらず、ゴラムという「依存症に完全に食われた先輩」が身代わりとなって破滅してくれる。これを依存症的に解釈すると、「あの人みたいにはなりたくない」という反面教師の存在がなければ、脱却は不可能だ、という残酷な現実を示しているわけである。フロドの勝利は純粋な意志力ではなく、依存症をこじらせた先輩が自爆したおかげ。禁酒会の古参が壮絶に壊れていく姿を見て「自分はやめなきゃ」と震える新米の図、と言えよう。
つまり『ロード・オブ・ザ・リング』は、現代的に言うと、中世ファンタジーをまとった依存症物語とも言える作品だ。英雄譚に見せかけて、実際は「やめられない! でもやめたい!」という全人類共通の悲喜劇を描いており、そこが観客を強く惹きつける理由だろう。
指輪を捨てる旅は、依存症者が「もう一回だけ」と呟きながらギャンブル台に向かう足を文字通り引き剥がしてくれる仲間との壮絶ロードムービーと捉えることができるかもしれない。