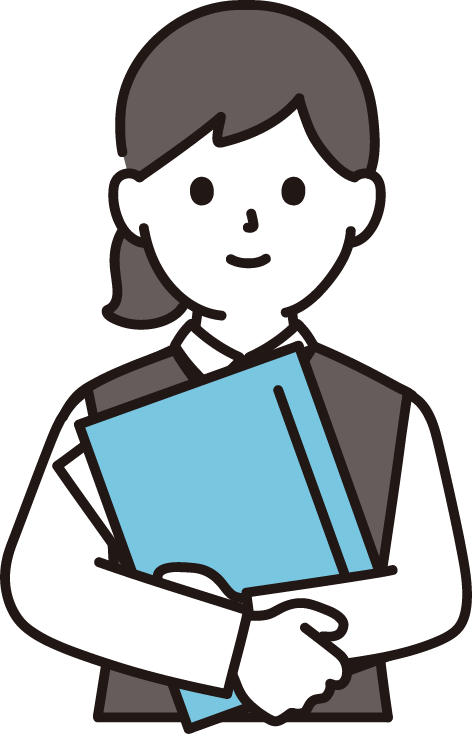
高齢者や判断能力が低下した方の財産や生活を守るために、成年後見制度は重要な役割を果たします。
司法書士は、ご本人やご家族が安心して暮らせるよう、財産管理や生活支援など、法的手続き全般をサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
成年後見制度を利用するには申立が必要
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に対し、本人の判断能力の状況に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」の選任を申し立てる必要があります。
司法書士は、家庭裁判所に提出するための書類作成や手続きのサポートを行います。これには、申立書の作成、必要書類の収集、家庭裁判所への提出などが含まれます。
あわせて読みたい

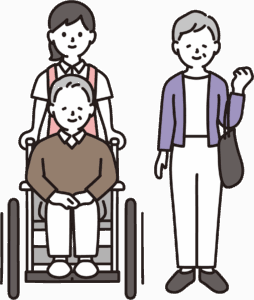
成年後見 後見・補佐・補助の申立
高齢者や判断能力が低下した方の財産や生活を守るために、成年後見制度は重要な役割を果たします。司法書士は、ご本人やご家族が安心して暮らせるよう、財産管理や生活...
成年後見人
役割と目的
- 成年後見人は、判断能力が不十分な方(主に認知症、高齢者、精神障害などで判断力が低下した方)の権利と生活を保護するために選任されます。
- この制度の主な目的は、本人が自分で適切な意思決定を行えない場合に、本人の財産管理や契約、医療行為に関する意思決定を代行することです。
成年後見人の業務内容
- 財産管理: 成年後見人は、本人の財産(不動産、預金、投資など)を管理します。売買契約、賃貸契約、銀行取引など、本人に代わって行う必要がある取引も多いです。
- 日常生活の支援: 本人が生活の中で困っていることに対し、支援を行います。例えば、日常的な支出管理や生活の決定支援などです。
- 医療・介護の意思決定: 医療や介護に関する選択を行うため、主治医と相談し、本人にとって最適な治療方針を決めることもあります。
設置方法
- 家庭裁判所に申立てを行い、審査を経て成年後見人が選任されます。
- 本人の意思や家族の意向が反映されることもありますが、最終的には家庭裁判所が選任します。
保佐人
役割と目的
- 保佐人は、判断能力が不十分だが成年後見人よりも軽度な障害がある方に対して設置されます。成年後見人のように全権を与えられるわけではなく、特定の事柄について支援を行います。
- 主に、判断能力が一部欠けているが、一定の支援が必要な方をサポートする役割を担います。
保佐人の業務内容
- 重要な契約の代理や同意: 例えば、高額な財産の売買や賃貸契約、借金の契約など、特に重大な契約に対して保佐人の同意が必要です。保佐人は、これらの契約について本人が理解しているかどうかを確認し、必要な支援を行います。
- 財産の管理: 成年後見人と同様に、本人の財産管理を行うこともあります。ただし、全面的な管理ではなく、特定の部分に限定されます。
設置方法
- 成年後見人と同様に、家庭裁判所に申立てを行い、選任されます。
- 本人が保佐人の設置を望まない場合もありますが、その場合でも、判断能力が不足していることが証明されると、家庭裁判所が設置を決定することがあります。
補助人
役割と目的
- 補助人は、保佐人よりも軽度の判断能力の不全がある人に対して設置されます。成人が自立的な生活を送る上で、少しのサポートがあれば十分な場合に、この制度が適用されます。
- 補助人は、特定の生活支援や意思決定の補助を行いますが、本人が自分で意思決定をする能力が高いため、支援範囲は限定的です。
補助人の業務内容
- 契約の補助: 本人が日常的な契約(例えば、買い物、交通機関の利用、保険契約など)を行う際、補助人がその契約内容についてアドバイスを行い、支援します。
- 支援範囲の明確化: 補助人が支援できる範囲は、具体的な契約や選択肢に関して、事前に定められます。支援内容は家庭裁判所によって詳細に定められ、不要な介入を避けるよう配慮されています。
設置方法
- 補助人も家庭裁判所に申立てを行い、選任されます。保佐人や成年後見人よりも支援の必要性が軽い場合に選ばれます。
まとめ
- 成年後見人は、判断能力が完全に欠けているか、非常に低い成人に対して全面的な支援を行います。財産管理や医療、日常生活全般を支援します。
- 保佐人は、判断能力が一部欠けている成人に対して、特定の契約に同意する権限や財産管理の支援を行います。
- 補助人は、軽度の判断能力不足がある成人に対して、特定の契約や意思決定の支援を行いますが、支援範囲は限られています。
いずれの制度も、本人を支援し適切なサポートを行うことが求められます。また、すべての制度は家庭裁判所の監督下で運営されており、不正や誤用を防ぐ仕組みが整えられています。
